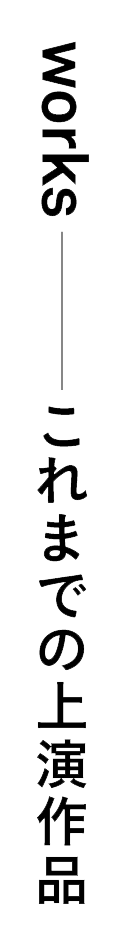
バイオ・グラフィ:プレイ(1984)
作 / マックス・フリッシュ
訳 / 松鵜功記
演出 / 矢野 靖人
レビュー
「バイオ・グラフィ:プレイ」では、過去のある時点に遡り、そこから改めて自分の行動を選択し直し、もう一度生き直すことができたら、ということを繰り返して見せた。今の自分の選択の、どこをどうやり直したらよかったのか、過去のある時点に戻り、少しずつ行動を変えた結果が何度も提示される。40年ほど前の戯曲だが、shelfの上演では決して古さを感じさせることなく、丁寧に戯曲に向き合って異なる選択がもたらした違いを繊細に提示して見せていた。コロナ禍というパンデミックに見舞われ、かつ、ウクライナでの戦争が不安を増幅させているなかでの上演は、人生の選択、生きる意味を真正面から問い直すような舞台として、深い余韻を残していたように思う。
演出ノート
「いいですか、あなたは現在に向かって行動していない、過去に向かっている。そこです。あなたは経験を通してすでに未来のことが分かっていると思っている。だから何度やっても同じ物語になる。」
(マックス・フリッシュ『バイオ・グラフィ:プレイ(1984)』松鵜功記/訳より)
物語。けっきょくのところ、私たち人間は、物語=言葉を通じてしか、”世界”に触れることが出来ない存在なのではないか。マックス・フリッシュの戯曲『私の伝記:演戯』の主人公、行動科学の教授ハンネス・キュアマンは、演出家(またはゲームマスター)の演出のもと、彼の人生が記録された伝記=テキストを参照しつつ、自分の人生をあらためて生き直そうと試みる。(しかし伝記とは?…そう、これもまた記された言葉であり物語ではないか!)
人は一般に、自分の人生をより劇的で、あるいはより美しく柔和で素晴らしいものにしたいと願う生き物だ。それが例え他人から見たら平凡で凡庸な人生に過ぎなくとも ―何故なら価値観は人によって異なるからであって、しかしその価値観すら言葉と物語で構築されているものなのだが、
そう。私たち人間は果たして、けっきょくのところ、既存の、ありふれた言葉で構築された過去という―それは人の記憶とも、あるいはもっと広く世界の歴史といってもいい―そのような物語の領域を抜け出して、今・ここにある/今・ここ”そのもの”である”現在”と向かい合うこと、即ち”世界”そのものに触れることの出来ない存在なのかも知れない。マックス・フリッシュの戯曲『私の伝記:演戯』を読んで後、私はそのようなことを思わざるを得なかった。
しかし、しかしだ、私は違う、そうではない、異なる人生の可能性を追求したい、それが例え失敗に終わるとしても試みることを諦めたくはない、そしてそれこそが、マックス・フリッシュが演劇のリハーサルのなかに見出したハプニングの魅力―少なくとも舞台上で展開する出来事は、可能性として複数存在する出来事のうちのひとつに過ぎないことを表現することは出来ないのか―へと連なる欲望であり、可能性の探求であり、そして何より現在、世界への憧れなのではないか。
私は現在に、即ち世界に直接に向かい合いたいのだ。この各所で分断され、互いに孤立し、他者を排除し、国家や社会があらゆるレイヤーでそれぞれの場所で自閉しつつあるこの現代社会を突破して、世界に直接に、他者と直にコミュニケートしたいのだ。そしてそれは、繰り返される人間の我々の愚かな歴史=物語を乗り越えるために必要な試みなのではないかと思うのだ。そして私は、演劇の上演には、その可能性がまだ残されていると信じているのだ。
マックス・フリッシュ(Max Frisch 1911-1991)について
スイスの劇作家、小説・散文作家。チューリヒ生まれ。第二次世界大戦の終結を目前に控えた1945年に劇作家としてデビュー、戦後のスイスとヨーロッパを鋭く批判する作家として注目される。『バイオ・グラフィ:プレイ』(1967/1984)のほかに演劇では、ナチ台頭を許したドイツおよびヨーロッパの市民社会を批判する『ビーダーマンと放火犯たち』(1958)、ユダヤ人差別問題を個人と手段が作り出す他者に対する偶像に問う『アンドラ』(1961)、などがある。散文では、個人の記録に虚構の物語、現代史的出来事への考察、文学・演劇論などを組み込んだ日記形式の作品『日記1946-1949』(1950)および『日記1966-1971』(1972)、多くの言語に翻訳され、世界的に読者を獲得した『シュティラー』(1954)、『ホモ・ファーバー』(1957)などがある。
















